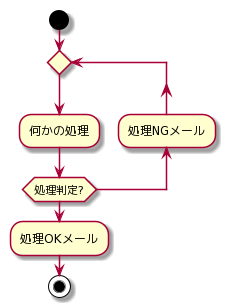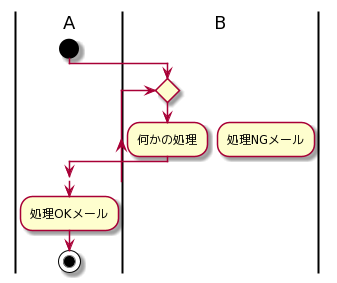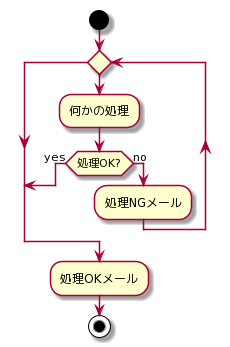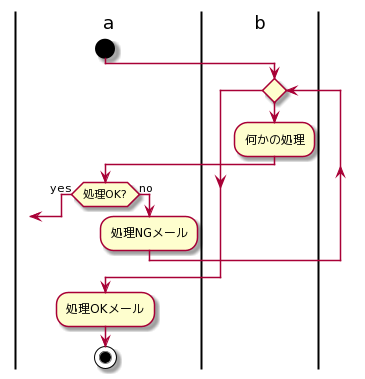娘が大学のゼミの先生に怒られたようでしゅんとしていた。
理由を聞くと、メールを出したら最初と最後の挨拶文がないからこれでは社会に出たらうんぬんかんぬん・・・・、と説教されたそうな。
まあ、普段仕事でメールで書いているように
●●様
いつもお世話になっております。
:
:
以上、よろしくお願いします。
てな感じでメールを書かないといけないしきたりを知らないので、Lineのように内容だけ送ったらしい。よくやってしまうパターン。
でもさ・・・・。
自分の場合はどうかというと、娘のことは言えない。お客さんにはメールでの挨拶不要と宣言してしまっている。
しかも、こちらからの作業の完了メールには御礼メールはいらない、何も返事がなければOKであるということにしている。
自分のメールはほぼチャットみたいな型式になっているので、とても短い。ATOKが一文字目で文章を呼び出してくれるので毎回、同じ文章で、10秒以内でメールを作って送っている。
でも、何でSlackのようなシステムではなくてメールを使うかというと、やはりお客さん側のシステムの縛りが厳しいからである。外部からへの連絡はメール以外は許していない。これを越えていこうとすると、大きな壁が立ちはだかるのである。そこでメールで速やかに連絡するする。
ここから昔の話し。爺になったせいか、昔のことをよく思い出す・・・・。
まだ電子メールなんて一般には使われていなかった時代の30年前の話しである。
まずLANというものを導入され、PC(そのころはNECのPC-9800シリーズ)が10BASE2(BNCコネクタの同軸ケーブル)でつながった。その工事をしたのは、みんながやりたがらなかったのでPCが詳しそうということで私が指名された。LANの上ではNOVELLのNetWareが動かしていた。しかも、UNIX系のワークステーション(Sun4だっけ?)とは、何かのゲートウェイで通信できるという画期的な(?)ネットワークだった。
さて、これからが笑い話。あるときある社内の記事録をメールで各所に送ったら、新しく赴任してきた総務担当の課長が怒鳴り込んできた。
送った本人であるから課長の話を聞いてみると、
「メールの宛先の順番が上司順に並んでいない!」
とのことだった。なるほど、メールアドレスの順番までも気になる人は気になるんだと思って、反論する前に感心してしまった覚えがある。
いろいろと面倒になる前に、別に議事録の中できちんと偉い順に名前が載っているからいいじゃないとか、理系がよくやってしまう技術的屁理屈とかの、訳のわからない理由で押し通したのあった。
このころはメールを使い始めだったので、そんなことがあったけど、今は反対にメールよりもLineとかSlackのようなチャットでコミュニケーションをしていくのが多いのではないかな? もしかしたら、メールアドレスを持っているけどメールを送ったことがない人もいるかもな。仕事でメールで連絡すると「まだメールなんて使っているの?」なんて言われたりして。
私からすると、最近のメールは迷惑メールだらけで、本当に必要なメールは受信したすべてのメールの100分の1以下になっている。必要なメールは迷惑メールやDMに埋もれてしまうから、頭のいいフィルタ機能が持ったメーラーがないと全く役に立たない。だからMozillaのメールはいただけない、Gmailはいいぞ。
もうそんな理由でメールは過去のコミュニケーションツールかもしれない、だけど、どこでも使えるツールや単なる通知としてはまだまだ残っていくのかな?