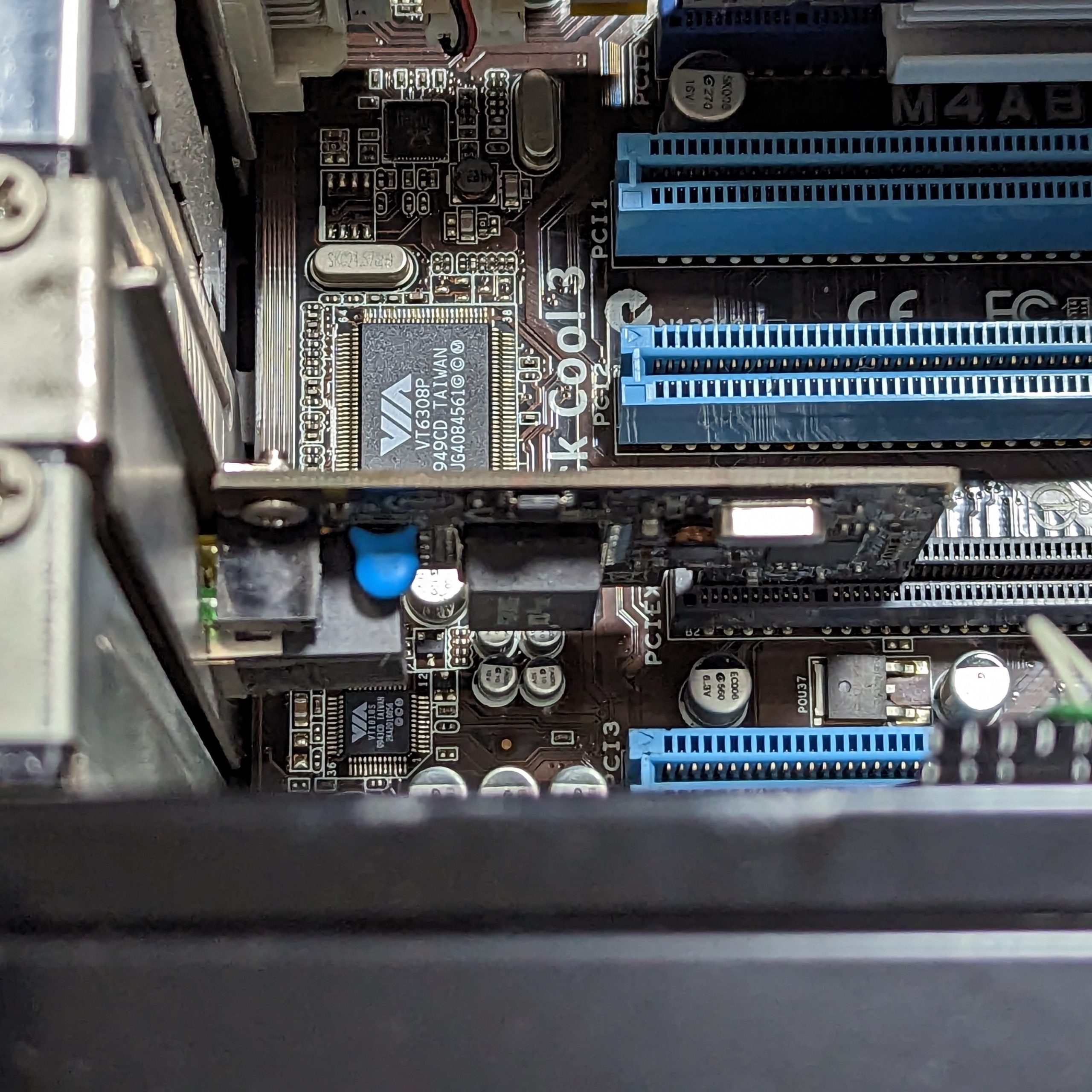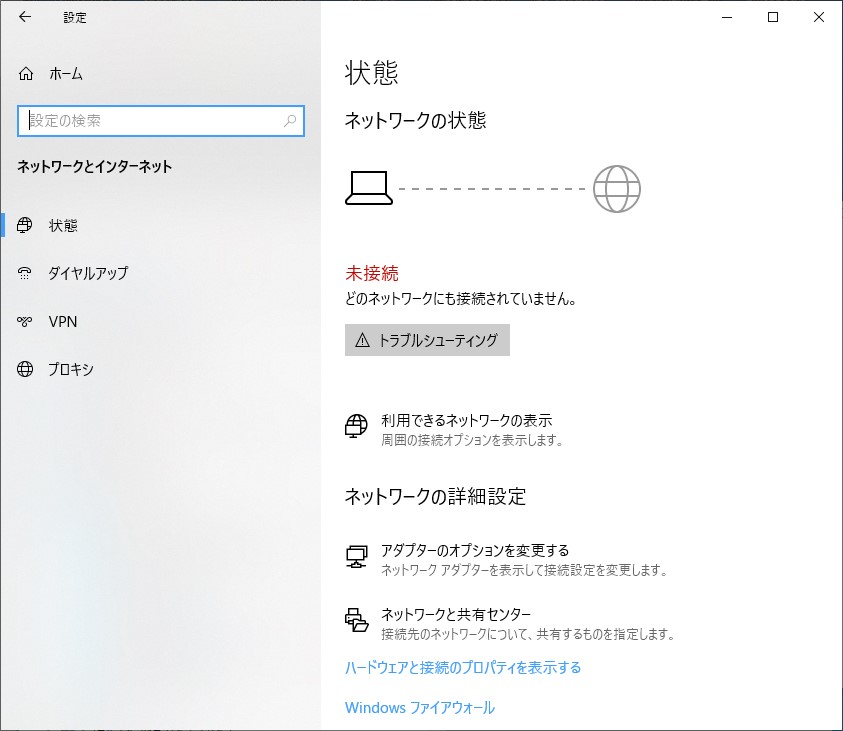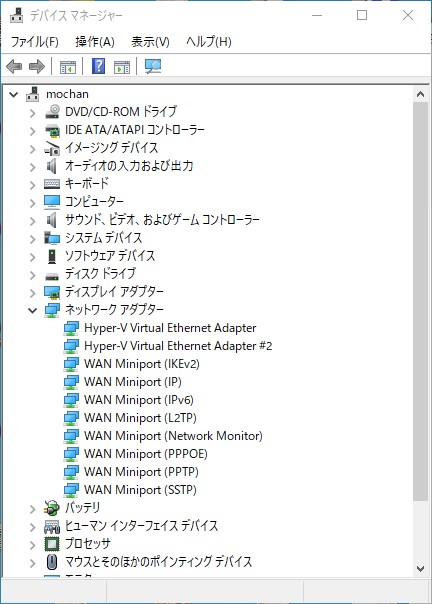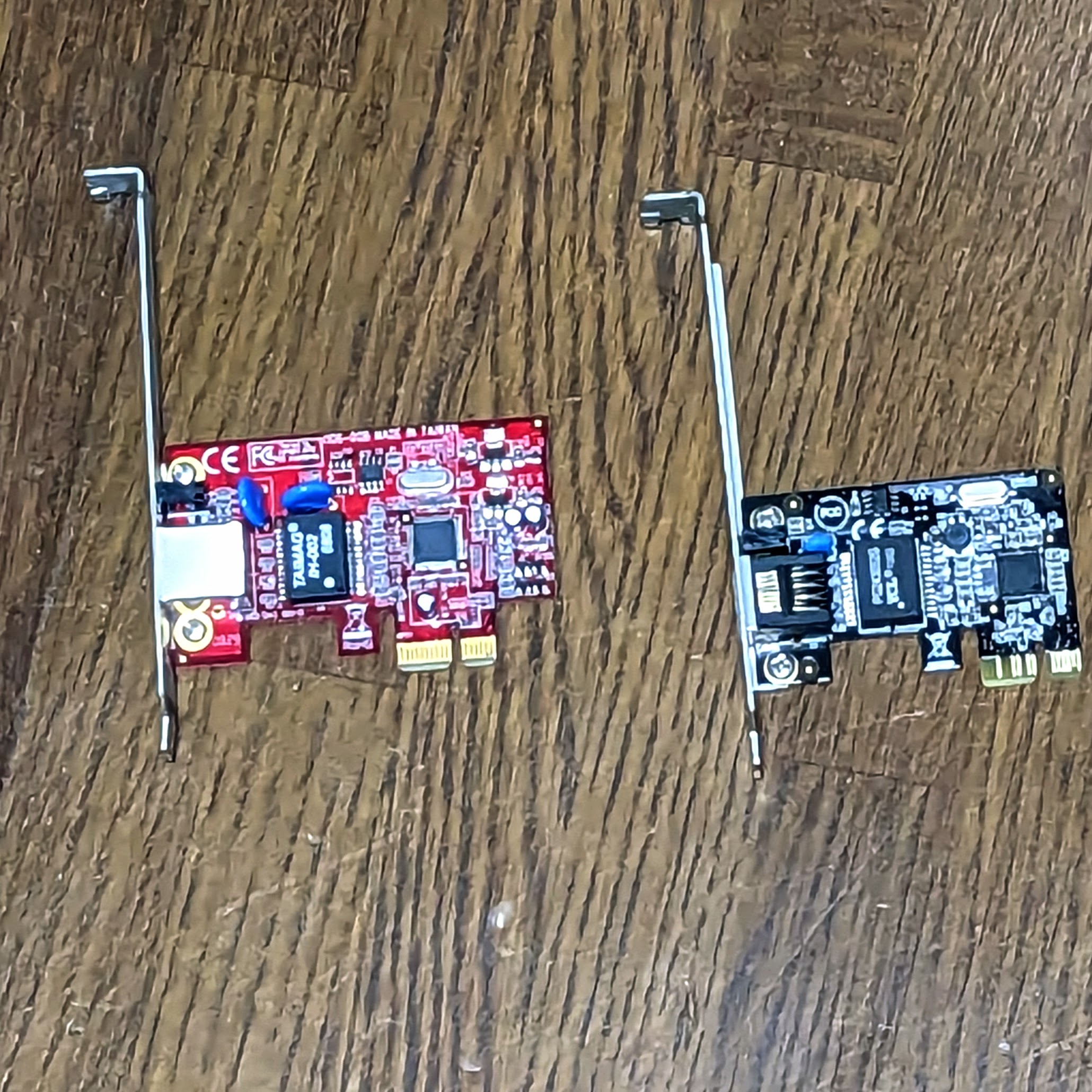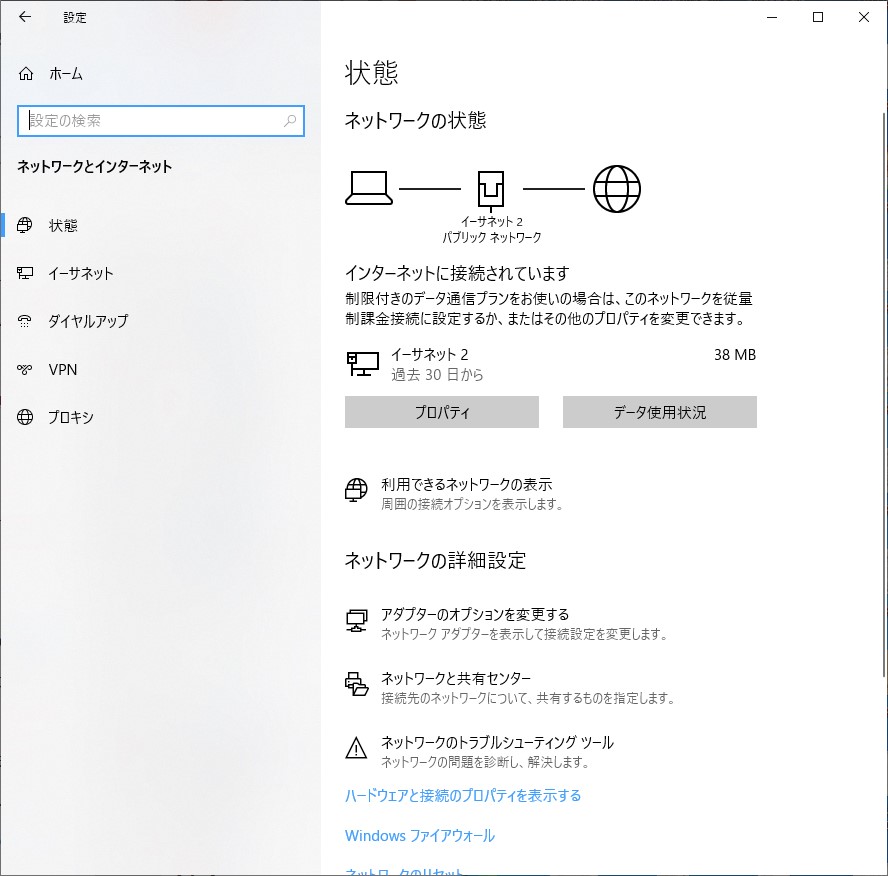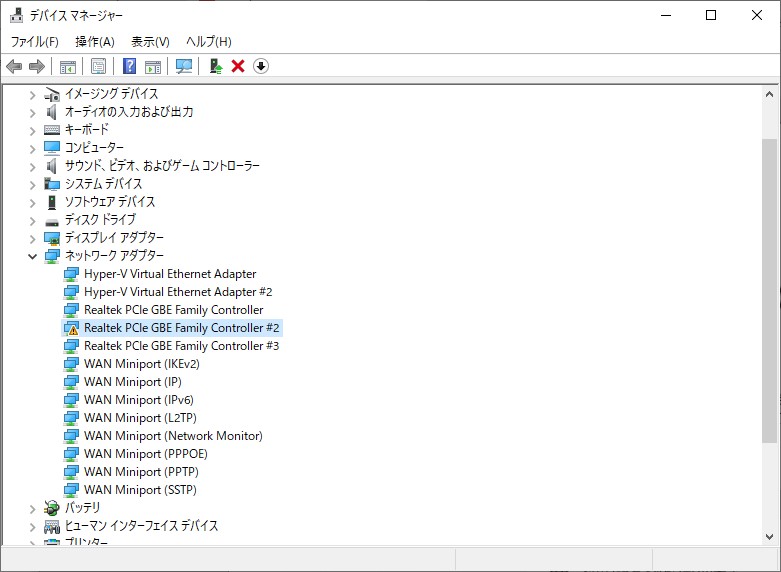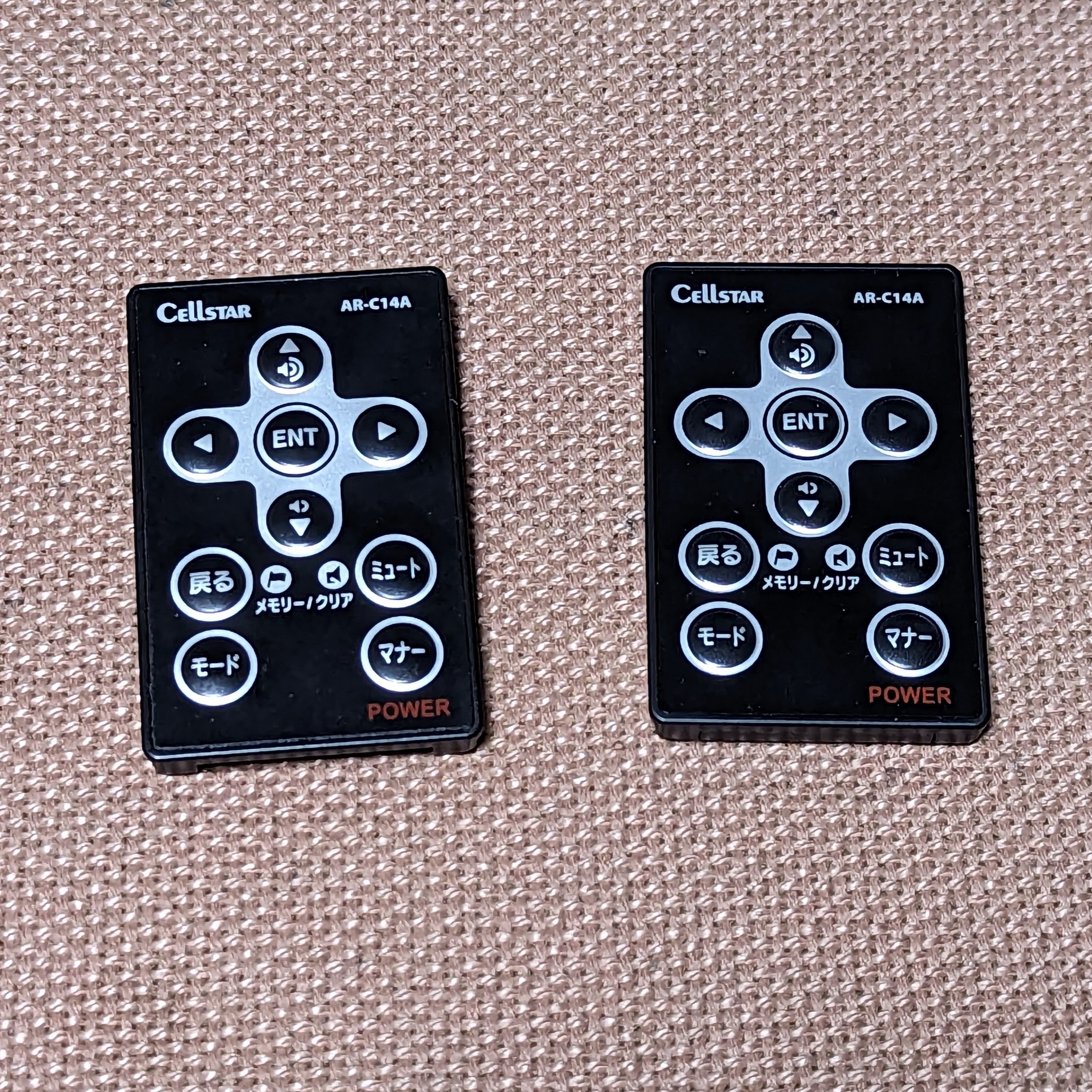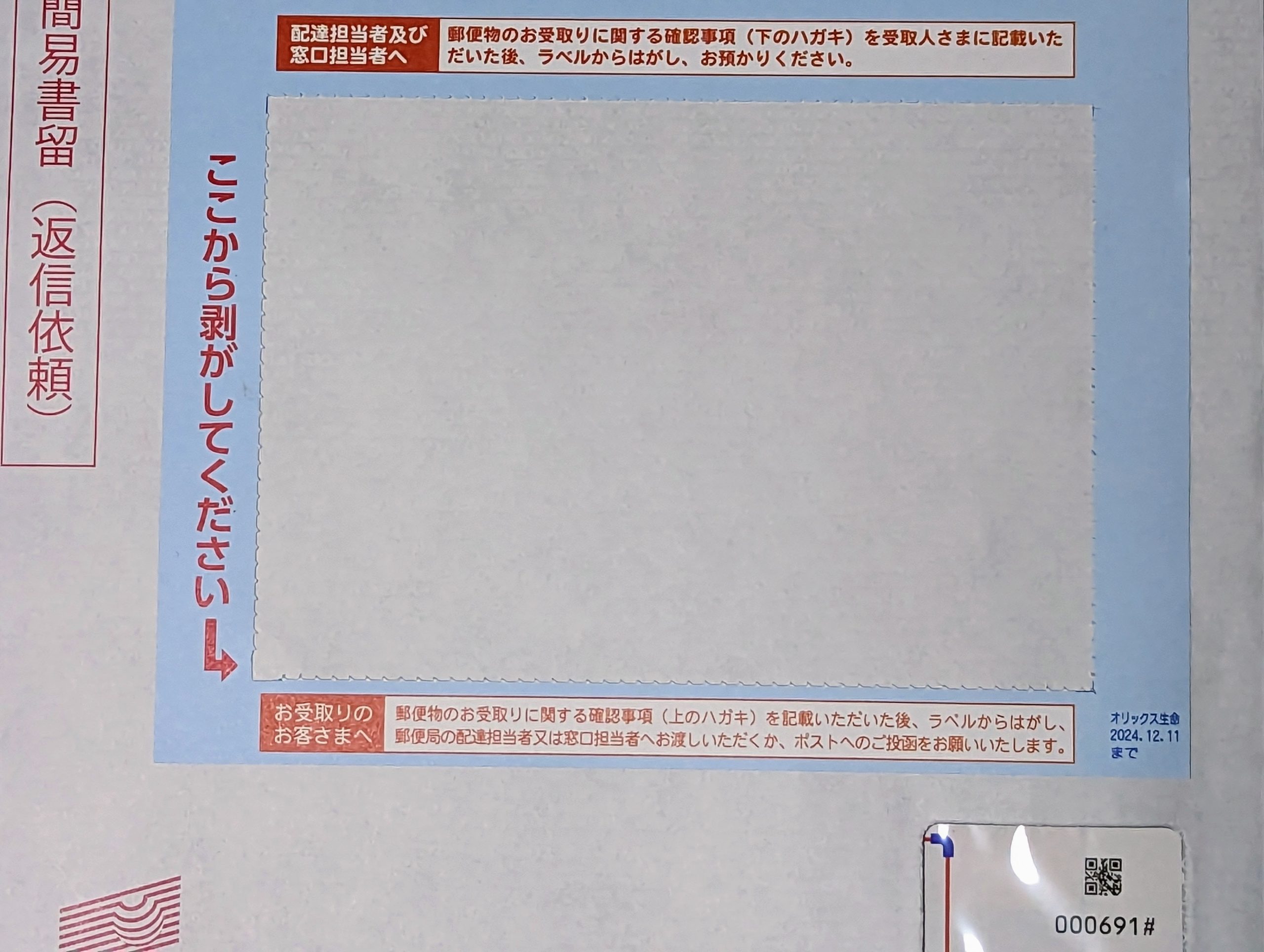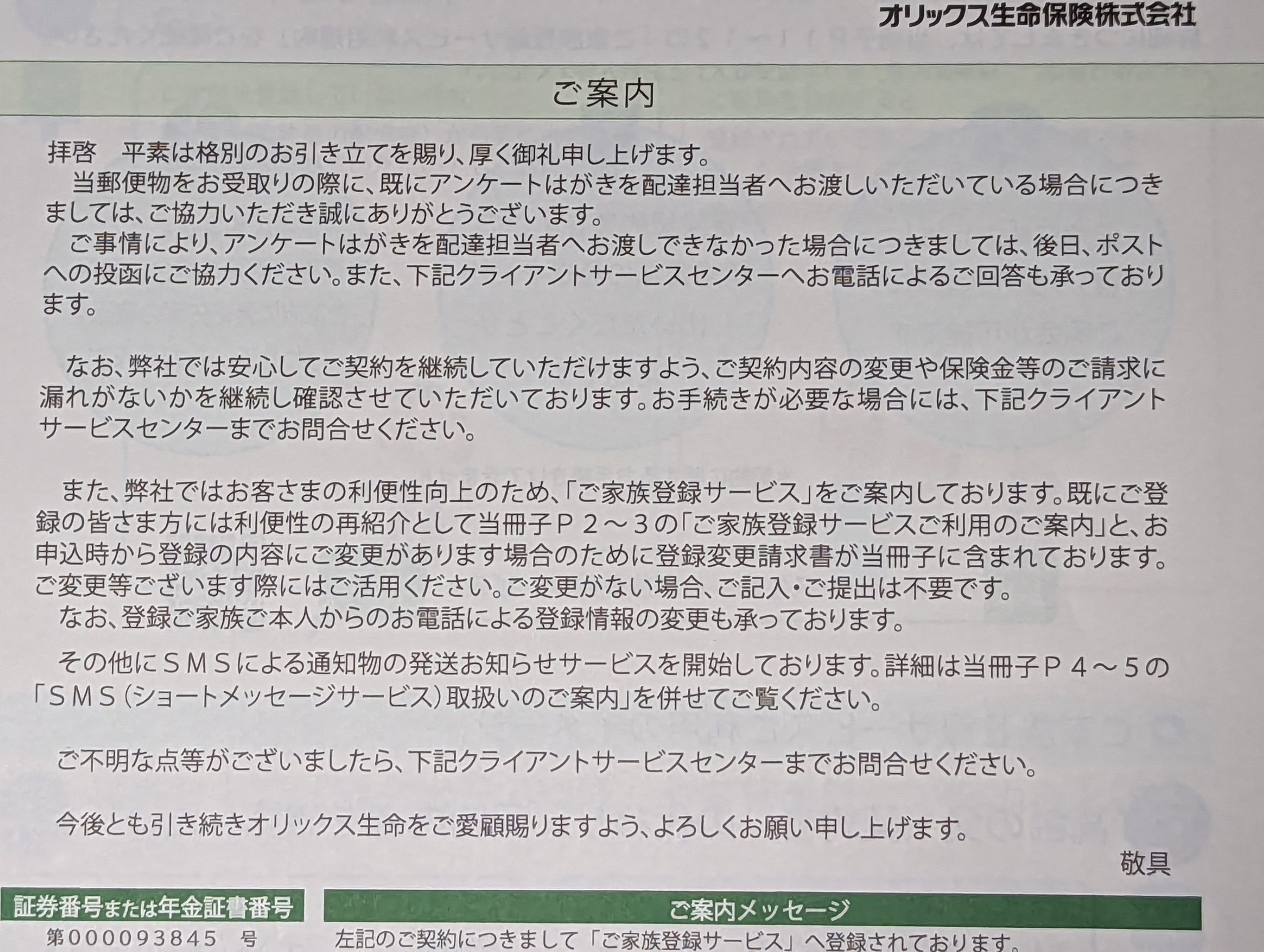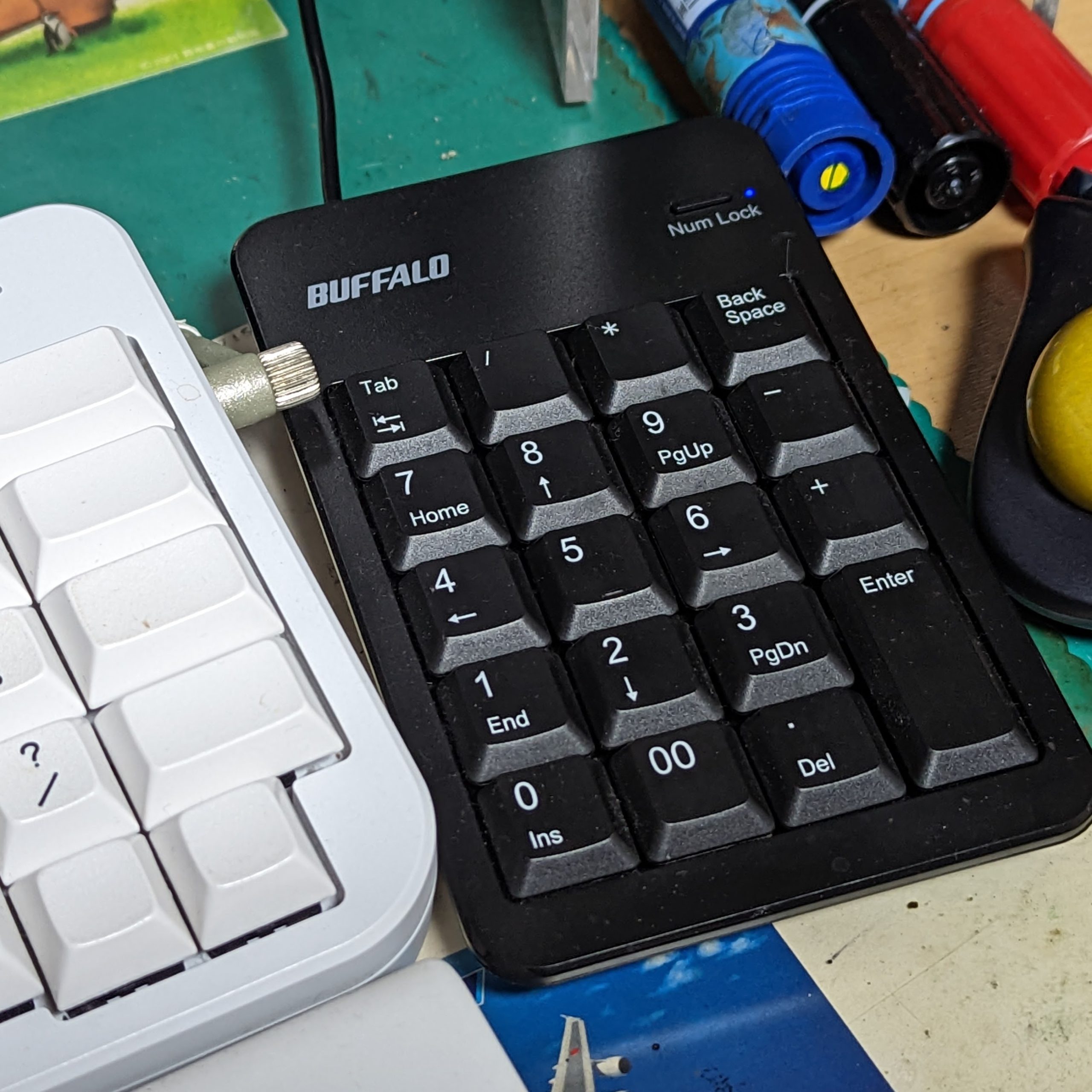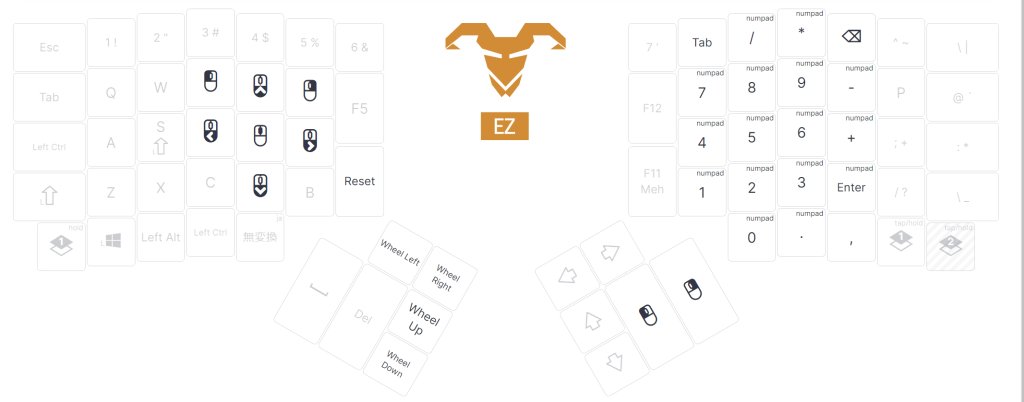大昔に買ったZIPPOのハンディウォーマーで手先を温めて仕事をしています。
最近、暖まらなくなりました。もう3シーズンも使っていますので、バーナー(口金)を交換しなければいけません。バーナーは所謂触媒のことです。
ZIPPOのハンディウォーマーは、こちらも所謂白金懐炉のことです。オリジナルのハクキンカイロは、笑顔のおじさんが目印です。
ZIPPOのハンディウォーマーのバーナーは、白金カイロの口金がそのまま使えます。ZIPPOブランドのバーナーよりもお安く手に入ります。購入するのは、こちらです。
口金もZIPPOブランドで揃えたかったら、こちらになります。ZIPPOの刻印が打ってあります。こちらを買った方が少しだけ安いですね。性能はどうなんでしょうか? 変わりないのでしょうか?
もっと言うと、口金はアマゾンではなくてヨドバシ.comでは一つだけでも購入できます。1~2シーズンで1個ですので、1個で十分でしょう。
ついでに、こちらの燃料用のベンジンも手に入れました。こちらもヨドバシ.comからです。どういうわけかアマゾンでは2本以上のセット買いしかありません。
ZIPPOのオイルライター用のオイルが手に入りやすいのですけど、高くなりますのでやめておきます。オイルもZIPPOブランドで揃えたかったら、こちらをどうぞ。
近くのお店ではカイロ用のベンジンが手に入りませんでした。手に入っても、しみ抜き用の小ボトルで安いのですけど、すぐに無くなります。

バーナーを交換した結果ですが、とてもよく発熱します。暖かいのが戻ってきました。燃えているのではなくて化学反応です。

これで今シーズンも乗り切れそうです。