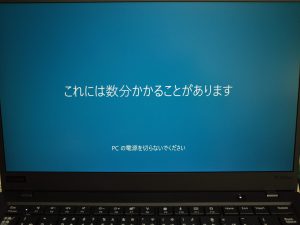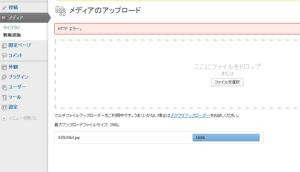今さらながら二段階認証のためにYubiKeyを購入した。今までは二段階認証にはGoogle認証アプリを使っていた。
サービスの中にはを二段階認証に使えないサービスもある。Evernoteとかセキュリティの設定画面でYubiKeyの設定がなさそうなのだけど、どこかにあるのかな?
Googleのログインは簡単になった。それとDropboxも。GoogleとDropboxはYubiKeyとGoogle認証アプリが併用できる。
パスワード管理のサービスを使っているけど、こちらはGoogle認証で二段階認証を設定しているところにYubiKeyの設定をすると、YubiKeyだけになってGoogle認証が使えなくなる。YubiKeyの設定を解除するとGoogle認証が使えるようになる。このことをサポートに聞いたら、これが仕様だそうだ。複数の二段階認証の入口を許さないことでセキュリティを高めているということなのか。
パスワード管理はYubiKeyを使わずに今まで通りGoogle認証アプリを使うことにする。6桁コードの認証コードを入れるのは面倒だけど、スマートフォンを無くさないと思うけど、小さなYubiKeyを無くしそうで心配だから。でも、スマートフォンって壊れるよね。結局どちらも心配だけど、これはいずれ考えるということで先送り・・・。
まだまだYubiKeyを使いこなせないという感じかな。一番の問題は、どうやってYubiKeyを持ち運ぶかということ。普段は家にいるし、自宅が電子キーなのでキーフォルダなんて持っていないしな。